あなたは「中央大学の共通テスト利用入試で何点取れば合格できるの?」と悩んでいませんか?結論、中央大学の共通テスト利用ボーダーは学部・学科により76%から89%の範囲で設定されています。この記事を読むことで各学部の詳細なボーダーラインと効果的な対策法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.中央大学共通テスト利用ボーダーとは何か
共通テスト利用入試の基本概要
中央大学の共通テスト利用入試は、大学入学共通テストの成績のみで合否を判定する入試制度です。
中央大学では「単独方式」と「併用方式」の2つの形態があり、単独方式は共通テストの成績のみで判定されます。
一方、併用方式は共通テストの成績と中央大学独自の個別試験の成績を合算して判定する方式となっています。
多くの学部で3教科型と4教科型の両方が設定されており、受験生は自分の得意科目に応じて選択できる仕組みになっています。
出願は複数の学部・学科に同時に行うことができ、検定料の減額制度も用意されているため、効率的な受験戦略を立てることが可能です。
ボーダーラインの仕組みと見方
ボーダーラインとは、河合塾などの大手予備校が予想する合格可能性50%のラインを指します。
A判定は合格可能性80%以上、B判定は65%、C判定は50%、D判定は35%となっており、ボーダーラインはC判定と同等の位置づけです。
共通テストの配点に対する得点率で表示されるため、例えば「80%」と表示されている場合、満点の80%の得点が必要という意味になります。
ただし、これらの数値は予想値であり、実際の入試では志望動向や問題の難易度により変動する可能性があることを理解しておく必要があります。
ボーダーラインを参考にして、安全圏を狙うなら+5%程度の余裕を持った目標設定をすることが重要です。
2025年度入試における中央大学の特徴
2025年度入試では、理工学部が2026年4月に3学部体制に再編される予定となっており、過渡期の入試となります。
新課程入試への対応として、旧教育課程履修者への配慮も行われており、旧課程科目での受験も可能となっています。
英語外部試験利用方式も多くの学部で実施されており、英検やTOEICなどの資格を活用した受験も選択肢の一つです。
全国7都市9会場で試験会場が設置されており、地方在住の受験生も受験しやすい環境が整備されています。
5学部共通選抜により、1回の試験で複数学部の合否判定を受けることができる効率的なシステムも大きな特徴となっています。
2.中央大学共通テスト利用ボーダー学部別一覧2025年度
文学部の共通テストボーダーライン
文学部の共通テスト利用ボーダーは比較的安定した水準を保っています。
単独4教科型では87%(522/600点)、単独3教科型では専攻により80%から89%の範囲で設定されています。
各専攻別の詳細なボーダーラインは以下の通りです:
- 国文学専攻:87%(435/500点)
- 英語文学文化専攻:85%(425/500点)
- ドイツ語文学文化専攻:85%(425/500点)
- フランス語文学文化専攻:83%(415/500点)
- 中国言語文化専攻:83%(415/500点)
- 日本史学専攻:88%(440/500点)
- 東洋史学専攻:82%(410/500点)
- 西洋史学専攻:87%(435/500点)
- 哲学専攻:87%(435/500点)
- 社会学専攻:88%(440/500点)
- 社会情報学専攻:87%(435/500点)
- 教育学専攻:86%(430/500点)
- 心理学専攻:89%(445/500点)
心理学専攻が最も高いボーダーとなっており、東洋史学専攻が相対的に狙い目となっています。
法学部の共通テストボーダーライン
法学部は中央大学の看板学部として、高いボーダーラインが設定されています。
法律学科の単独5教科型では87%(522/600点)、単独3教科型では92%(644/700点)と非常に高い水準です。
学科別の詳細なボーダーラインは以下の通りです:
- 法律学科(単独5教科型):87%(522/600点)
- 法律学科(単独3教科型):92%(644/700点)
- 法律学科(学部別併用):86%(430/500点)
- 国際企業関係法学科(単独5教科型):82%(492/600点)
- 国際企業関係法学科(単独3教科型):84%(588/700点)
- 国際企業関係法学科(学部別併用):83%(415/500点)
- 政治学科(単独5教科型):87%(522/600点)
- 政治学科(単独3教科型):89%(623/700点)
- 政治学科(学部別併用):84%(420/500点)
単独3教科型は配点が高く設定されているため、得点率も高くなる傾向があります。
併用方式を活用することで、より現実的な合格ラインでの挑戦が可能となります。
経済学部・商学部の共通テストボーダーライン
経済学部は中央大学の中でも人気の高い学部で、安定したボーダーラインを維持しています。
経済学部の単独3教科型では学科により85%から89%、単独4教科型では88%の水準となっています。
経済学部の学科別ボーダーライン:
- 経済学科(単独3教科型):90%(630/700点)
- 経済学科(単独4教科型):88%(792/900点)
- 経済情報システム学科(単独3教科型):88%(616/700点)
- 国際経済学科(単独3教科型):89%(623/700点)
- 公共・環境経済学科(単独3教科型):89%(623/700点)
商学部(フレックス)の学科別ボーダーライン:
- 経営学科(単独3教科型):85%(425/500点)
- 会計学科(単独3教科型):86%(430/500点)
- 国際マーケティング学科(単独3教科型):87%(435/500点)
- 金融学科(単独3教科型):80%(400/500点)
金融学科が相対的に狙い目となっており、国際マーケティング学科が最も高いボーダーとなっています。
理工学部・国際情報学部の共通テストボーダーライン
理工学部は2026年4月に3学部体制への再編が予定されており、現在は過渡期となっています。
理工学部の学科により76%から90%と幅広い範囲でボーダーが設定されています。
理工学部の学科別ボーダーライン:
- 数学科(学部別併用):84%(126/150点)
- 物理学科(単独):89%(623/700点)
- 都市環境学科(単独):91%(546/600点)
- 精密機械工学科(単独):84%(588/700点)
- 電気電子情報通信工学科(単独):87%(609/700点)
- 応用化学科(単独):84%(588/700点)
- ビジネスデータサイエンス学科(単独):86%(516/600点)
- 情報工学科(単独):90%(630/700点)
- 生命科学科(単独):84%(588/700点)
- 人間総合理工学科(単独):86%(516/600点)
国際情報学部のボーダーライン:
- 国際情報学科(単独3教科型):88%(308/350点)
- 国際情報学科(単独4教科型):86%(387/450点)
- 国際情報学科(学部別併用):91%(273/300点)
情報工学科と都市環境学科が最も高く、生命科学科や応用化学科が相対的に狙い目となっています。
総合政策学部・国際経営学部の共通テストボーダーライン
総合政策学部は中央大学の中でも比較的ボーダーが低く設定されており、狙い目の学部と言えます。
両学科とも78%から79%という水準で、他学部と比較して合格しやすいボーダーとなっています。
総合政策学部の学科別ボーダーライン:
- 政策科学科(単独):83%(291/350点)
- 政策科学科(学部別併用):82%(246/300点)
- 国際政策文化学科(単独):83%(291/350点)
- 国際政策文化学科(学部別併用):82%(246/300点)
国際経営学部のボーダーライン:
- 国際経営学科(単独3教科型):85%(340/400点)
- 国際経営学科(単独4教科型):84%(420/500点)
- 国際経営学科(学部別併用):80%(240/300点)
総合政策学部は併用方式を活用することで、より現実的な合格ラインでの受験が可能となります。
国際経営学部も同様に併用方式の活用により、80%台前半での合格が狙える水準となっています。
3.中央大学共通テスト利用入試の方式と対策
単独方式と併用方式の違い
単独方式は共通テストの成績のみで合否が決まる方式で、大学独自の試験を受験する必要がありません。
この方式の最大のメリットは、共通テスト一発勝負で複数の大学・学部に出願できる効率性にあります。
一方で、ボーダーラインが高く設定される傾向があり、確実性を求める場合は高得点が必要となります。
併用方式は共通テストと中央大学独自の個別試験の成績を合算して判定する方式です。
この方式では共通テストの配点比率が下がるため、個別試験で挽回する機会があり、ボーダーラインも相対的に低くなります。
ただし、追加で個別試験の対策が必要となり、受験日程の調整も重要なポイントとなります。
受験生は自分の得意分野や学習進度に応じて、どちらの方式を重視するかを決定することが重要です。
教科数による入試方式の選び方
3教科型は多くの学部で実施されており、文系受験生にとって最も一般的な受験パターンです。
英語・国語・選択科目(地歴公民または数学)の組み合わせが基本となり、効率的な学習が可能です。
4教科型は3教科に加えて理科または数学を追加する方式で、より幅広い学力が求められます。
5教科型は法学部で実施されており、国公立大学と同様の科目数での受験となります。
教科数が多いほど競争相手が絞られる傾向があるため、得意科目が多い受験生には有利に働きます。
逆に、特定科目に特化して学習したい場合は、教科数の少ない方式を選択することが戦略的です。
自分の学習状況と志望学部の特徴を踏まえて、最適な教科数の方式を選択することが合格への近道となります。
狙い目学部・学科の見つけ方
ボーダーラインが相対的に低い学部・学科を見つけることで、合格可能性を高めることができます。
総合政策学部は78%から79%と中央大学の中でも最もボーダーが低く、第一の狙い目となります。
理工学部では生命科学科や応用化学科が84%と比較的低く設定されており、理系志望者にとって狙い目です。
商学部(フレックス)の金融学科は80%と商学部の中では最も低いボーダーとなっています。
文学部では東洋史学専攻が82%と他専攻と比較して低く、人文系志望者の狙い目と言えます。
国際経営学部の併用方式は80%台前半と、国際系学部としては比較的低いボーダーが設定されています。
これらの学部・学科は競争倍率も相対的に低い傾向があるため、戦略的な出願先として検討する価値があります。
出願戦略のポイント
複数学部への出願により、合格可能性を最大化することが中央大学受験の基本戦略です。
5学部共通選抜を活用することで、1回の試験で複数学部の合否判定を受けることができます。
安全校・適正校・挑戦校のバランスを考慮して、ボーダーラインの異なる学部・学科を組み合わせることが重要です。
検定料の減額制度を活用し、2つ目以降の出願は15,000円で行うことができるため、積極的な併願が可能です。
併用方式と単独方式を組み合わせることで、異なる試験形式での挑戦機会を確保できます。
出願時期や試験日程を考慮して、他大学との併願スケジュールを調整することも重要な要素です。
志望順位制度を活用し、合格した場合により希望度の高い学科への進学を確保する戦略も有効です。
4.中央大学共通テスト利用で合格するための実践対策
目標得点率の設定方法
ボーダーラインに5%程度の余裕を加えた得点率を目標として設定することが基本的な考え方です。
例えば、ボーダーが85%の学部を志望する場合、90%以上を目標とすることで安全圏での合格を狙えます。
志望学部のボーダーラインを複数年分調査し、上昇傾向にあるかどうかを把握することが重要です。
模試での成績推移を分析し、現在の実力とのギャップを明確にして学習計画を立てることが必要です。
科目別の得点バランスを考慮し、苦手科目の底上げと得意科目の更なる向上を両立させる戦略が効果的です。
共通テスト本番での失敗リスクを考慮し、複数の目標設定(最低ライン・目標ライン・理想ライン)を設けることが重要です。
定期的な目標見直しにより、学習進度に応じた現実的な目標調整を行うことが合格への近道となります。
科目別の効率的な学習法
英語は配点が高いため、リーディングとリスニングの両方でバランス良く得点することが重要です。
長文読解力の向上には毎日の音読練習と語彙力強化を継続し、リスニングは様々なアクセントに慣れることが必要です。
数学は基礎計算力の徹底と頻出パターンの習得により、確実な得点を積み重ねることが重要です。
国語は現代文の論理的読解力と古典の基礎知識を並行して学習し、時間配分の練習も欠かせません。
理科は理論の理解と問題演習のバランスを取り、計算問題と記述問題の両方に対応できる力を養います。
社会科目は通史の理解を基盤として、テーマ史や地域史などの横断的な学習により知識を深化させます。
過去問演習と模試を通じて実戦感覚を養い、時間内での効率的な解答技術を身につけることが全科目共通の重要ポイントです。
併願校選定における中央大学の位置づけ
中央大学は早慶上智とMARCH諸大学の中間的な位置づけとして、多くの受験生の併願校となっています。
法学部を志望する場合、上智大学法学部や早稲田大学法学部との併願が一般的なパターンです。
経済・商学系志望者は明治大学や青山学院大学の同系統学部との併願により、選択肢を広げることができます。
理工系志望者は東京理科大学や芝浦工業大学などの理工系大学との併願により、専門性を重視した進路選択が可能です。
総合政策学部は早稲田大学国際教養学部や慶應義塾大学総合政策学部の併願校として機能します。
国公立大学志望者にとっては、私立大学の確実な合格校として重要な位置づけとなります。
地方国公立大学と私立大学の両方を視野に入れた併願戦略において、中央大学は安定した選択肢として活用できます。
合格可能性を高める受験計画の立て方
年間学習計画を3期に分けて段階的な目標設定を行い、着実な実力向上を図ることが重要です。
基礎固め期(4月〜8月)では各科目の基本事項を徹底し、共通テストレベルの基礎力を完成させます。
実戦演習期(9月〜12月)では過去問演習と模試受験により、実戦的な解答力と時間管理能力を向上させます。
直前対策期(1月)では最終調整と体調管理に重点を置き、本番での最高パフォーマンスを目指します。
定期的な模試受験により現在の実力を客観的に把握し、学習計画の修正を適切に行います。
弱点科目の克服には集中的な学習期間を設け、得意科目の維持には継続的な練習を欠かさないことが重要です。
受験本番に向けた体調管理と精神的なコンディション作りも、学習計画と同様に重要な要素として位置づけます。
まとめ
この記事で解説した中央大学共通テスト利用ボーダーの重要ポイントをまとめます:
- 中央大学の共通テスト利用ボーダーは学部・学科により76%から89%の範囲で設定されている
- 法学部が最も高いボーダー(92%)で、総合政策学部が最も低い(78%〜79%)
- 単独方式は共通テストのみ、併用方式は個別試験も含む2つの受験方式がある
- 狙い目学部は総合政策学部、理工学部の生命科学科・応用化学科、商学部金融学科など
- 目標得点率はボーダーライン+5%程度の余裕を持って設定することが重要
- 英語の配点が高いため、英語での高得点が合格の鍵となる
- 5学部共通選抜により1回の試験で複数学部の合否判定を受けられる
- 併願戦略では安全校・適正校・挑戦校のバランス良い組み合わせが重要
- 年間学習計画を段階的に設定し、定期的な見直しを行うことが効果的
中央大学の共通テスト利用入試は、戦略的な学部選択と計画的な学習により、確実に合格を掴むことができる入試制度です。この記事で紹介したボーダーライン情報と対策法を参考に、あなたも中央大学合格という目標に向かって頑張ってください。適切な準備と戦略があれば、必ず良い結果につながるはずです。
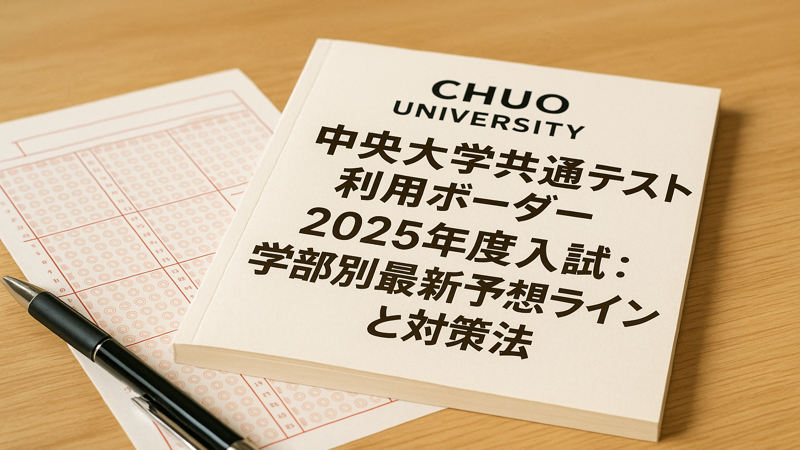
コメントを残す