あなたは「令和6年度っていつからいつまでなの?」と疑問に思ったことはありませんか?結論、令和6年度は2024年4月1日から2025年3月31日までの期間です。この記事を読むことで令和6年度の正確な期間や重要なスケジュール、実用的な活用方法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1. 令和6年度はいつからいつまで?基本期間を解説

令和6年度の正確な開始日と終了日
令和6年度は、2024年4月1日から2025年3月31日までの12ヶ月間を指します。
これは日本の標準的な年度区分に従ったもので、国や地方自治体の会計年度と同一の期間となっています。
令和6年度の開始時点では、まだ令和6年(2024年)ですが、年度の後半は令和7年(2025年)に入ることになります。
そのため、年度名は開始年の元号を使用するという日本独特のルールがあります。
具体的な日時で表現すると、令和6年4月1日0時00分から令和7年3月31日23時59分59秒までが令和6年度の正確な期間です。
令和6年度と西暦の対応関係
令和6年度を西暦で表現すると、2024年度または2024年4月〜2025年3月となります。
国際的な文書や外国企業との取引では、西暦表記の方が理解されやすいため、「2024年度」と記載することが一般的です。
令和6年度の期間中に含まれる主な時期は以下の通りです:
- 2024年4月〜12月:令和6年度前半(令和6年中)
- 2025年1月〜3月:令和6年度後半(令和7年中)
このように年度と暦年がずれることで、書類作成時に混乱しやすいポイントでもあります。
特に2025年1月以降の日付を記載する際は、令和7年であることを忘れずに確認しましょう。
令和6年度の呼び方と表記方法
令和6年度は複数の呼び方や表記方法があり、使用場面によって使い分けることが重要です。
公的文書では「令和6年度」、ビジネス文書では「令和6年度」または「2024年度」、国際的な場面では「FY2024」(Fiscal Year 2024)という表記が使われます。
また、決算期を基準とした表記では「令和7年3月期」と呼ばれることもあります。
これは事業年度の終了月を基準とした呼び方で、特に企業の決算資料などでよく見られる表現です。
法的書類や契約書では、「令和6年4月1日から令和7年3月31日まで」と正確な期間を明記することが求められる場合もあります。
2. 年度と年の違いと令和6年度の特徴

年度と暦年(年)の基本的な違い
年度と年は似ているようで全く異なる概念であり、正しく理解することで書類作成時の混乱を避けることができます。
「年」は1月1日から12月31日までの暦年を指し、これは世界共通の時間区分です。
一方、「年度」は特定の目的のために設定された12ヶ月間の期間で、国や組織によって異なる開始月を持ちます。
日本では4月1日から翌年3月31日までを一般的な年度期間としており、これは明治時代の制度改革時に定められたものです。
例えば、令和6年2月は「令和6年」かつ「令和5年度」に属し、令和7年2月は「令和7年」かつ「令和6年度」に属することになります。
なぜ4月始まりが一般的なのか
日本で4月始まりの年度が採用されている理由は、明治時代の財政制度改革にさかのぼります。
当時、政府の税収の多くを占めていた地租(土地税)の徴収時期に合わせて、年度開始を4月に設定したのが始まりです。
農業中心の社会では、秋の収穫後に税を納めることが自然であり、その後の会計整理期間を考慮して4月開始となりました。
現在でもこの制度が継続されている理由として、以下の要因があります:
- 学校教育制度との整合性
- 企業の採用活動との連動
- 予算編成と執行のサイクル
- 法改正の施行時期との調整
多くの企業も国の会計年度に合わせることで、税務処理や官公庁との取引を円滑に行えるメリットがあります。
令和6年度に含まれる具体的な月の詳細
令和6年度に含まれる各月の詳細と、その時期に発生する主要な出来事を整理すると以下のようになります。
| 月 | 西暦 | 和暦 | 主な出来事・特徴 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2024年4月 | 令和6年4月 | 年度開始、入学式、新年度予算スタート |
| 5月 | 2024年5月 | 令和6年5月 | ゴールデンウィーク、労働保険年度更新準備 |
| 6月 | 2024年6月 | 令和6年6月 | 労働保険年度更新、住民税決定通知 |
| 7月 | 2024年7月 | 令和6年7月 | 夏季賞与、源泉所得税納付(特例) |
| 8月 | 2024年8月 | 令和6年8月 | 夏季休暇、お盆休み |
| 9月 | 2024年9月 | 令和6年9月 | 上半期終了、中間決算準備 |
| 10月 | 2024年10月 | 令和6年10月 | 下半期開始、最低賃金改定 |
| 11月 | 2024年11月 | 令和6年11月 | 年末調整準備、来年度予算編成 |
| 12月 | 2024年12月 | 令和6年12月 | 年末調整、冬季賞与 |
| 1月 | 2025年1月 | 令和7年1月 | 新年、源泉所得税納付(特例) |
| 2月 | 2025年2月 | 令和7年2月 | 確定申告開始、来年度準備 |
| 3月 | 2025年3月 | 令和7年3月 | 年度末、卒業式、決算処理 |
この表からわかるように、令和6年度は令和6年と令和7年にまたがる期間となっています。
官公庁と企業で異なる年度設定
官公庁は基本的に4月1日から翌年3月31日までの年度を採用していますが、企業は自由に事業年度を設定できます。
国税庁の統計によると、日本企業の約20%が3月決算(4月開始)を採用していますが、12月決算(1月開始)を採用する企業も多く存在します。
企業が事業年度を決める際の主な考慮要因は以下の通りです:
- 業界の繁忙期を避けた決算時期の設定
- 税理士との調整のしやすさ
- 親会社や取引先との年度統一
- 消費税免税期間の最適化
- 資金繰りと納税時期のバランス
特に外資系企業では、本国の年度に合わせて12月決算とするケースが多く見られます。
一方、建設業や小売業では、業界特有の繁忙期を避けて決算月を設定することが一般的です。
3. 令和6年度の重要スケジュールと行事

学校関連の令和6年度主要行事(入学式・卒業式)
令和6年度の学校関連行事は、全国的にほぼ統一されたスケジュールで実施されます。
入学式・始業式は2024年4月上旬(主に4月8日前後)に開催され、新しい学年のスタートを切ります。
卒業式・修了式は2025年3月中旬から下旬(主に3月18日〜25日)にかけて実施され、令和6年度の学業を締めくくります。
学期制については、多くの学校で以下のスケジュールが採用されています:
- 1学期:2024年4月〜7月(夏休み前まで)
- 2学期:2024年9月〜12月(冬休み前まで)
- 3学期:2025年1月〜3月(春休み前まで)
夏休みは7月20日頃から8月末まで、冬休みは12月25日頃から1月8日頃まで、春休みは3月25日頃から4月7日頃までが一般的です。
また、令和6年度は大学入学共通テストが2025年1月18日・19日に実施される予定となっています。
税務関連の令和6年度重要日程
令和6年度の税務関連手続きには、法人と個人それぞれに重要な期限が設定されています。
法人税関連では、3月決算法人の令和6年度分法人税申告期限が2025年5月31日となります。
所得税関連では、令和6年分(2024年分)の確定申告期間が2025年2月16日から3月17日まで実施されます。
消費税については、令和6年度分の申告期限が事業年度終了日から2ヶ月以内となり、3月決算の場合は2025年5月31日が期限です。
住民税関連のスケジュールは以下の通りです:
- 令和6年度住民税決定通知:2024年6月頃
- 第1期納付期限:2024年6月末
- 第2期納付期限:2024年8月末
- 第3期納付期限:2024年10月末
- 第4期納付期限:2025年1月末
固定資産税については、令和6年度分の納税通知書が2024年4月〜6月に送付され、年4回の分割納付が可能です。
労働保険・社会保険の令和6年度手続き時期
令和6年度の労働保険年度更新手続きは、2024年6月3日から7月10日まで実施されました。
この期間中に、事業主は前年度の労働保険料の確定申告と当年度の概算申告を行う必要があります。
社会保険関連では、以下のスケジュールが重要です:
- 健康保険・厚生年金保険料率:2024年3月分(4月納付分)から適用
- 雇用保険料率:2024年4月1日から適用
- 労災保険料率:2024年4月1日から適用
算定基礎届(定時決定)は、2024年7月1日から10日までに提出期限が設定されており、4月〜6月の平均報酬月額を基に標準報酬月額が決定されます。
年末調整関連業務は2024年12月に実施され、源泉徴収票の交付期限は2025年1月31日となります。
特に令和6年度は定額減税の実施により、年末調整の手続きが複雑化しているため、事前の準備が重要です。
令和6年度の祝日カレンダー
令和6年度に含まれる祝日は、合計で16日間設定されています。
2024年(令和6年)4月〜12月の祝日:
- 昭和の日:4月29日(月)
- 憲法記念日:5月3日(金)
- みどりの日:5月4日(土)
- こどもの日:5月5日(日)
- 海の日:7月15日(月)
- 山の日:8月11日(日)
- 敬老の日:9月16日(月)
- 秋分の日:9月23日(月)
- スポーツの日:10月14日(月)
- 文化の日:11月3日(日)
- 勤労感謝の日:11月23日(土)
2025年(令和7年)1月〜3月の祝日:
- 元日:1月1日(水)
- 成人の日:1月13日(月)
- 建国記念の日:2月11日(火)
- 天皇誕生日:2月23日(日)
- 春分の日:3月20日(木)
ゴールデンウィークは2024年4月27日(土)から5月6日(月)まで最大10連休となり、多くの企業や学校で長期休暇が設定されます。
4. 令和6年度で知っておくべき実用的な活用方法

書類作成時の令和6年度正しい記載方法
令和6年度に関する書類を作成する際は、正確な表記方法を理解しておくことが重要です。
公的書類では「令和6年度」と記載し、西暦併記が必要な場合は「令和6年度(2024年度)」と表記します。
契約書や重要文書では、期間を明確にするため「令和6年4月1日から令和7年3月31日まで」と具体的な日付を記載することが推奨されます。
国際的な文書や外資系企業との取引では「FY2024」(Fiscal Year 2024)または「2024年度」という表記が適切です。
書類作成時の注意点として、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 年度と年の混同を避ける
- 開始年の元号を使用する(令和6年度)
- 必要に応じて西暦を併記する
- 期間を明確にする場合は具体的日付を記載
- 相手方の表記に合わせる柔軟性を持つ
特に2025年1月以降の日付を記載する際は、令和7年であることを確認し、令和6年度に属することを明記する必要があります。
令和と西暦の簡単変換テクニック
令和と西暦の変換は、覚えやすい計算方法を使うことで素早く行うことができます。
西暦から令和への変換は「西暦の下2桁 − 18 = 令和」という公式を使います。
例えば、2024年の場合:24 − 18 = 6(令和6年)、2025年の場合:25 − 18 = 7(令和7年)となります。
令和から西暦への変換は「令和 + 18 = 西暦の下2桁」という逆算で求められます。
この「18」という数字は「レイワ(018)」の語呂合わせで覚えやすく、実用的な変換方法として多くの人に活用されています。
年度の変換では、以下の対応表を参考にしてください:
- 令和6年度 = 2024年度 = 2024年4月〜2025年3月
- 令和7年度 = 2025年度 = 2025年4月〜2026年3月
- 令和5年度 = 2023年度 = 2023年4月〜2024年3月
スマートフォンのメモ機能に「令和 = 西暦下2桁 − 18」と保存しておくと、必要な時にすぐ確認できて便利です。
令和6年度の学年早見表の見方
令和6年度の学年早見表は、教育関係者だけでなく、習い事や各種申込みの際に役立つ重要な情報です。
令和6年度(2024年4月〜2025年3月)における各学年の生年月日は以下の通りです:
| 学年 | 生年月日 |
|---|---|
| 小学1年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日生まれ |
| 小学2年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日生まれ |
| 小学3年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日生まれ |
| 小学4年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ |
| 小学5年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ |
| 小学6年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日生まれ |
| 中学1年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ |
| 中学2年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日生まれ |
| 中学3年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ |
| 高校1年生 | 2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ |
| 高校2年生 | 2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ |
| 高校3年生 | 2006年4月2日〜2007年4月1日生まれ |
注意点として、4月1日生まれの児童・生徒は前の学年に属することを覚えておきましょう。
これは、4月1日0時に年齢が加算されるため、入学時点で既に6歳(または12歳、15歳)に達しているという法的解釈によるものです。
年度をまたぐ手続きで注意すべきポイント
年度をまたぐ手続きでは、特に期限や有効期間に関して注意深く確認する必要があります。
令和6年度末(2025年3月31日)で有効期限が切れる資格や許可証については、早めの更新手続きが必要です。
会計処理においては、2024年度の経費として計上できるのは2025年3月31日までに発生した費用に限られます。
予算執行の観点では、令和6年度予算は2025年3月31日までに執行完了する必要があり、未執行分は原則として翌年度に繰り越せません。
年度をまたぐ契約や取引で注意すべき点:
- 契約期間の明確化(年度内完結か継続契約か)
- 支払い条件の確認(年度内支払いか翌年度支払いか)
- 成果物の納期設定(年度末納期の実現可能性)
- 税務上の取り扱い(年度帰属の明確化)
- 予算の年度区分(当年度予算か翌年度予算か)
特に公的機関との取引では、年度末の3月に業務が集中するため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
まとめ
この記事を通じて、令和6年度に関する重要なポイントが明確になりました:
- 令和6年度は2024年4月1日から2025年3月31日までの期間
- 年度と年は異なる概念で、令和6年度は令和6年と令和7年にまたがる
- 4月始まりの年度制度は明治時代の財政制度改革に由来している
- 学校行事、税務手続き、労働保険など重要なスケジュールが年度単位で設定されている
- 書類作成時は年度と年の混同に注意し、正確な表記を心がける
- 西暦と令和の変換は「下2桁−18」の公式で簡単に計算できる
- 学年早見表では4月1日生まれが前学年に属することに注意が必要
- 年度をまたぐ手続きでは期限や予算執行に特別な配慮が必要
令和6年度の正確な理解は、日常生活からビジネスまで幅広い場面で役立ちます。この記事で得た知識を活用して、スムーズな手続きや書類作成を行い、充実した令和6年度をお過ごしください。
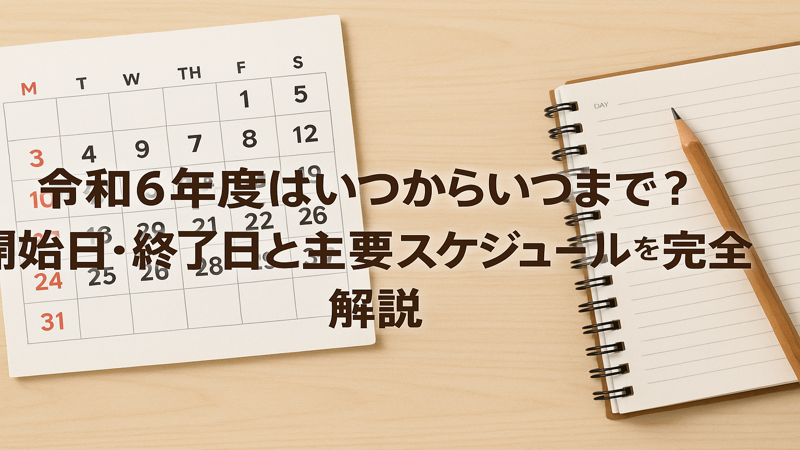
コメントを残す